700年以上の伝統技術と世界が目を見張る革新的なアイデアで、さらなる進化をもたらす木桶職人を訪ねて
ANAORI:まずは自己紹介をお願いします。
ANAORI:お祖父さま、お父さま、そして中川さん。その経緯と、代々に亘る様式の変化について教えてください。中川:木桶を製作しています「中川木工芸」の中川周士と申します。うちの始まりは、祖父が京都の老舗の木桶工房にでっち奉公という形で入門するところからで、そのでっち奉公を始めた頃から百年くらい経っているといわれています。
中川:祖父が木桶の仕事に入った、でっち奉公をしていた頃は、日本人の生活の中で木桶が日常的にたくさん使われていた時代で、お風呂の桶であったり、ご飯のおひつであったり、お寿司の桶であったり、味噌や醤油、たらいまで。ほんまに一軒の家に数十個ぐらい桶があったんじゃないかといわれていた時代ですけど、そこから父がその跡を継いで、僕へと移っていく中で、どんどん木桶が日常生活の中で使われなくなってきた。
プラスチック製品であったり、工業製品というものに取って代わられるような流れがあります。そういう中でうちは、日常雑器と呼ばれていたそういうものをおもてなしの器として、料理屋さんや旅館で使っていただけるように、非常に美しい桶を作り上げることを選択したことによって、今も残ることができたと考えています。
祖父がでっち奉公していた頃は、京都市内だけで250軒ぐらい桶屋があったといわれています。それが今、残っているのはほんまに数軒で、四軒か五軒。急激に下降していった業界です。そういう大きい桶を使う生活が変わっていく中で、うちの父はその木桶の技術を展開して美術工芸品というものを立ち上げていくことによって、2001年に人間国宝・重要無形文化財保持者の認定を受けました。
人間国宝は個人認定で工房認定ではないので、僕の仕事と父の仕事を明確に区切るという意味合いで、僕自身が2003年に滋賀の地に自分の工房を構えました。京都の父親のいるところの中川木工芸と滋賀の中川木工芸比良工房と二つの工房体制、今制作を進めているところです。

ANAORI:中川さんは、どのように修行されたのですか?どういう形でその技を習得されたのですか?
中川:父に師事する形で木桶の技術をマスターしました。正式には大学卒業後ですけど、ほんまに幼少期というか、まだ小学校に行く前から遊び場が工房でした。遊ぶ道具は、鉋屑やったり木っ端やったり、物を切ったり削ったり貼ったりということで遊んでいたので、その遊びの延長線上に自然と仕事が身に付いて、大学を卒業する頃には、もう特に修行をしなくても木桶作りに従事できるようになっていました。
ANAORI:技術の習得とは別に、どういう分野に関心をお持ちでしたか?どういうトレーニングをなされましたか?
中川:トレーニング、何ていうのかな。思春期の頃、レールが敷かれた所をそのまま走っていくのに、ちょっと抵抗心みたいなのが出てきて。。。幼稚園、小学校の低学年ぐらいは、お祖父ちゃんや親父に「周士は木桶、継ぐか?」と言われて、「継ぐ」と言ったら喜んでくれていたんで、そんなふうに言っていたと聞くんですけど。でもやっぱ思春期になってくると反抗心みたいなのもあって、違う世界を見てみたいという思いから、大学は美大へ進んで、現代美術の中の鉄の彫刻を勉強しました。そっちの世界に、ちょっと可能性を探ったというときもありました。
祖父はでっち奉公で、親父は高卒で、要は職人というのは一年でも早く修行して、職に就く方が身に付くという思いがあるから、大学は行く必要はないとは散々言われていたんですけども、そこをそのまま、やはり高卒で木桶の仕事に就くのに抵抗があって、それで大学を選択しました。反対されていたので、ちょっと言い訳がてら「美大やったら卒業しても桶に役立つことも学べる」と、半分だましながら、あわよくばなにか別の道があればという思いで大学に進んで。それで現代彫刻の世界を勉強した。
ただ、大学を四年間通って一番何を思ったかというと、僕自身、やっぱり物を作ることがすごく好きだったんだというのを再確認して、そうすると家業という、ものづくりの場に生まれたことに少し反抗的な思いがあったのが、むしろ卒業する頃にはそれはラッキーだったよね、というふうに思えるようになって。卒業後は、普通に木桶の仕事につきました。ただ、大学で勉強したこともやっぱり興味深いところやったんで、二足のわらじのような形で進んでいきました。卒業後、自分の彫刻のアトリエを、プレハブを借りて構えました。平日の朝8時から夜11時ぐらいまで毎日木工の仕事をして、土日をその代わりに休みにしてもらって、土日にアトリエへ行って泊まり込んで、鉄の彫刻を作るという生活を大学卒業後10年以上続けた形となります。
ANAORI:その彫刻は今でも作られていますか?
中川:やめたつもりはないですけれども、特に2003年に自分の工房を立ち上げてからは、木工のほうがあまりにも忙しくなり過ぎて、彫刻活動はできてないのが現実です。ただ、その彫刻から間が20年近く開いている形ですけど、面白いなと思うのは、時代が一つ変化してきて、アートの世界と工芸の世界が今、ミックスされてきたような時代になって。今も展示していますけれど、いわゆる現代アート展に木桶職人として作品を出すことが最近起こってきて。時代の流れは不思議で、工芸と美術は20年くらい前まではくっきりと別の世界のものだったものが、この20年でそれが混ざってきているのが面白い現象だと思います。

ANAORI:美術と工芸の関係について教えてください。近年、デザインという分野が重要視され、今となっては何でもデザインといういわれます。美大で勉強された中川さんが、美術品を、そしてデザイン・プロダクトを作られるとき、元となる意匠は何ですか?デザインという考え方と分野に対して、木桶職人としてどういう思いがありますか?
中川:伝統工芸の職人さんは、割とデザインに対して毛嫌いするというか、水と油のように、はじき合うみたいなところがあります。特に頑固な職人さん、伝統的で頑固な職人さんはそういう傾向があります。でも僕自身はやっぱり大学でデザインも現代アートも、そして工芸も勉強してきたので、僕の中ではそこにあまりボーダーがないです。だから自然にデザインと工芸を結びつけることができたのは、ある意味、僕の強みなのかと思います。
一般的に伝統工芸のデザイン・プロジェクトで失敗するのは、職人さんたちにものすごい有名な偉いデザイナーさんを連れてきて、一日工房をめぐって、数週間後にデザイン案がファックスでべらっと送られてきて、「物を作れ」みたいなことがあって、職人さんは言われたとおりに作ります。でもやっぱり、一方的に図面だけ、あるいは、工房の仕事の一部だけしか分からないデザイナーとのコラボレーションは、僕から見て成功しない例の方が多いと思います。
だから僕は、デザイン側からデザインが来て、それをその通り作ることはせずに、あるいは、コラボレーションするデザイナーには一度じっくり話し込むとか、じっくり工房を案内する、要するにその技術を理解した上でデザインして欲しいと思っているので、そういう関係性を紡ぐことに尽力しています。
私自身、例えばnendoの佐藤オオキさんとコラボレーションしたことがあるんですけど、彼のデザインは美しいんですよね。それをどう実現していくか。彼も工房に何度か訪れてくれて、夜遅くまで形について議論することもしましましたけど、そういう中で彼が提案してきたことが、桶の常識を破るような提案で。
桶はこういうふうにタガが複数本入って、その間に底が入るのが普通ですけど、彼が上げてきたデザインがあまりにも美し過ぎたので、それをどうすれば実現できるのかを一ヵ月近く考えました。結論としては、てこの原理を使うことによって、タガが一本でも二本の効果を出せることに気づいて、それにより作品を作ることで、彼のデザインを実現することができた経緯がありました。その関係はすごい面白い。
今まで700年、800年続いているこの木桶の技術が、まだ新しく更新する可能性があった、それに気がついたことが、デザイナーとのコラボレーションの中で生まれたと考えています。

ANAORI:伝統的な木桶作りにおいて、図面らしきものはありますか?
中川:伝統的な木桶に図面はないです。お祖父ちゃんの代から引き継いできた寸法帳というものがあって、そこには数字だけが書いてある。桶の直径、高さ、タガ1、底1、手が付いていたら手の位置、このような形で十個くらいの数字が羅列されてる帳面があって、それを見て作ることが多かった。基本的に桶は丸い形なので、コンパスで丸を描けばそれだけで図面になってしまうので、図面を起こす必要がなかったんです。でも僕自身が木桶を新しいものに生まれ変わらすことで、木桶の技術とデザインをミックスしていく中で、三角形であったり、葉っぱのような形であったり、今までにないような桶を作っていく中で図面が必要になってきました。その図面の精度が非常に高度である必要性を感じるようになって、そうすると手書きの図面よりもパソコンの図面、パソコンでも3DのCADみたいなもので形を検証していくようなことも始めて。そういうところで昔は図面が必要なかったんですけど、最近はそういう新しい技術も取り込んだ図面のようなもの、あるいは3Dモデルのような物を使うようになりました。
ANAORI:一方、道具は変化しましたか?まず桶作りの歴史において、数百年の歴史においていろんな変化があったと思いますが、例えば中川さんのお祖父さまと中川さんとの間で使っている道具は違いますか?
中川:基本的には祖父の代からほとんど変わってないです。一部、新しい機械、こういう電動の工具は導入していますけど、でもそれは桶を作るのにあまり使えなくて、大体もう八割くらいは古い道具を使います。ここの後ろにも並んでいますけど、こういう鉋は、祖父が使っていたやつもいまだに使っているし、祖父の師匠から受け継いだものやと200年ぐらい前からあります。
逆にこういう木工の業界の中でも、多分鉋を持っている数は、桶屋が一番多いと思います。大工さんであったり指物師であったり、平たいものを削る人は一つの鉋で、幅が広くても狭くても同じ鉋を使えるけど、桶の場合、丸みによって全部鉋が変わってくるので、直径が3センチくらいのもの、10センチぐらいのもの、30センチぐらいのもの、3メートルぐらいのものがあって、大体うちで今、数えたら300丁を超えるぐらいの鉋が必要になる。でも逆に言えば、これだけたくさんの鉋を持っているから、デザイナーがこういう形にしたいと言われた時に、それに対応できる鉋があるというところですね。それでも、もう新しく鉋屋さんに鉋を作ってもらうということもたびたびありますけど。

ANAORI:工芸の分野によっては道具屋さんがだんだん減っていて問題になっている。美術においてもそうだと思います。桶作りの場合は、道具屋さんとの付き合いはどういう状況にありますか?
中川:それは桶屋も違わず、僕らの仕事よりも道具を作る職人さんたちが減ってきているのは大問題で、まだ辛うじて残ってはいるんですけど、ほぼ壊滅に近いような状態。桶屋も減っているけど、さっき祖父の頃、250軒くらい桶屋があったって言ってて、その250軒の桶屋があったら、桶屋で使う鉋を作る職人さんたちがそれの10分の1ぐらい、20軒くらいあったので、それで経済としては成り立っていました。それが五軒になっちゃうと一軒も養えないような状態になるので、逆にこれからそこが問題になってくる。
ただ、最近やっぱりそういうことが取りざたされるようになってきて、そういう職人にスポットがすごく当たってきている中、若い子たちや違う職業をされてる方たちが出てきました。例えばうちが今取り組んでいるのは、刀鍛冶屋さんが作る、木を割る鎌がありますけど、それもカーブしているので桶屋特殊の物です。それをいわゆる野鍛冶と呼ばれる農作業で使う鍬や鋤みたいな物を作る職人さん、これもほぼ壊滅していたんですけど、そういう人にうちの道具を作ってもらうということを試み初めているところです。それが「野鍛冶復活プロジェクト」です。
鍛冶屋さんも面白くて、野鍛冶と刀鍛冶の二種類があります。刀鍛冶はまさに切れ味と美しさを追求していく。野鍛冶は農作業の鍬や鋤、鎌とかもそうなんですけど、むしろ質実剛健というか、美しさよりも強さを求める。やっぱり刀鍛冶の方はスポットがあたりやすいのでよく残っています。だから刀鍛冶の人に今までうちの桶を、こういうのを作ってくださいと、桶専門の鍛冶屋さんじゃないけどお願いしていました。桶はやっぱり元々は、生活一般の中で雑器として作られてたので、野鍛冶の方が相性がいいんですよね。それで野鍛冶の人にそういう道具を作ってもらったり。そういうことは始めてます。
インタビューの中編、後編は近日公開予定です。ご期待ください。
フォトグラファー:公文健太郎
プロフィール
中川周士中川木工芸/ 日本 1968年京都市生まれ。1992年京都精華大学美術学部立体造形卒業。卒業と同時に中川木工芸にて父・清司氏(人間国宝、重要無形文化財保持者)に師事。2003年より三代目として滋賀県大津市にある中川木工芸比良工房を主宰。 |
 |
1996年:京都美術工芸展 優秀賞受賞
1998年:京都美術工芸展 大賞受賞
2001年から2005年まで、京都造形芸術大学非常勤講師として勤務
2010年:ドンペリニヨン公式シャンパンクーラーを制作
2016年:神代杉KI-OKE STOOLが英国ロンドンV&A美術館の永久コレクションとなる
2017年:神代杉KI-OKE STOOLがパリ装飾美術館の永久コレクションとなる
2017年:ロエベクラフトプライズ ファイナリスト選出
2021年:第1回日本和文化グランプリ グランプリ受賞
2021年:第13回創造する伝統賞 受賞
さその他、国内外での個展、グループ展多数。京都の若手伝統工芸職人集団 GO ON に結成当初から参加。

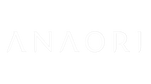
![Interview with Shuji Nakagawa of NAKAGAWA MOKKOUGEI [first part]](http://anaori.com/cdn/shop/articles/nakagawa_57.jpg?v=1665734078&width=3000)



